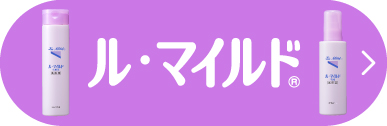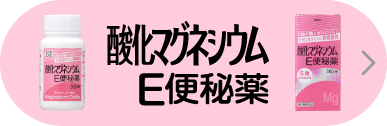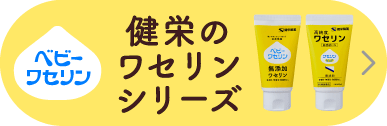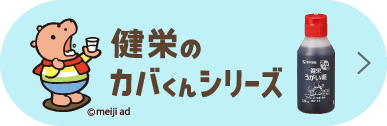1日中靴を履き続ける機会が多いと、においが発生しやすくなります。靴のにおいが気になり、何とかしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
靴のにおいの主な原因は、靴の中で繁殖した雑菌です。そのため、靴のにおいを防止するためには、「除菌する」「なるべく雑菌をつけない」「雑菌の繁殖を抑える」といった対策が必要になります。
今回は、靴のにおいの具体的な原因、においを消す方法と、靴・足のにおいを防ぐ方法を紹介します。専用のグッズだけでなく、家庭にあるものを利用する方法もあるのでぜひ参考にしてください。
靴のにおいの原因
靴のにおいの具体的な原因は以下になります。
- ・足から出る汗・皮脂
- ・生乾き・通気性の悪さによる雑菌
それぞれの原因を詳しく解説します。
足から出る汗・皮脂
靴のにおいの根本原因は雑菌です。足から出る汗や皮脂、角質などは雑菌の餌となるので、菌の繁殖を促します。足の裏には汗腺が多く、1日に出る汗の量はコップ1杯ともいわれています。
また、足が汗や皮脂、角質が溜まりやすい構造なのも、においが発生しやすいポイントです。爪と指の間や爪の湾曲した部分には皮脂や垢などが溜やすく、足の爪が伸びている方や、巻き爪の方はとくに注意が必要です。
生乾き・通気性の悪さによる雑菌
雑菌は高温多湿な環境で繁殖します。靴の中は空気がこもる上に、汗で湿度が高くなるので、雑菌の好む環境になりやすいです。
通気性が低くなりがちな靴の素材には、革製・ゴム製・ビニール製があげられます。注意したい靴の形状は、長靴・ブーツです。
また、生乾きの靴下や靴は、靴の中の環境をより悪化させます。靴や靴下は十分に乾燥させてから履きましょう。
靴のにおいを消す方法
靴のにおいを消す主な方法は以下のとおりです。
- ・洗剤や重曹(炭酸水素ナトリウム)を使って洗う
- ・消臭スプレー・消臭パウダーを靴につける
- ・靴に丸めた新聞紙を入れる
- ・重曹を使う
詳しく紹介するので、自身が手軽にできる方法から試してみましょう。
洗剤や重曹(炭酸水素ナトリウム)を使って洗う
濡らしても問題のない靴なら、洗剤や重曹を使って洗いましょう。丸洗いすれば、においの元となる雑菌を根本から除去できます。
汚れた靴は、まず靴専用の洗剤につけ置きをしてから靴用ブラシで擦りましょう。重曹と洗濯用洗剤をまぜて、漬け置きしてからブラシで擦るのもおすすめです。
洗濯洗剤・重曹の分量の目安は、お湯1リットルに対し、重曹が大さじ3杯、洗濯洗剤はキャップ1杯です。
がんこな汚れがある場合には、重曹と水で重曹ペーストをつくりましょう。ペーストを汚れに付け、ブラシで擦るとよく落ちます。
洗った後は、よく乾燥させるのがポイントです。あらかじめ水分を拭き取ってから、風通しの良い日陰に干してください。
最近では、靴専用の洗濯機が設置してあるコインランドリーもあります。手間を省きたい方は利用すると良いかもしれません。
消臭スプレー・消臭パウダーを靴につける
短時間でにおいを消したい場合には、消臭スプレー・消臭パウダーがおすすめです。靴用の消臭スプレーや消臭パウダーを使えば、スムーズに靴のにおいを消せます。
コンパクトサイズかつ速乾タイプのスプレーを持ち歩けば、外出先でも使用可能です。除菌・抗菌作用がある商品を選べば、根本の雑菌対策にもなります。
靴に丸めた新聞紙を入れる
靴に丸めた新聞紙を入れるのも、手軽なにおい対策の1つです。インクには消臭作用がある上に、新聞紙が靴の中の湿気を吸収してくれます。
しかし、同じ新聞紙を長期間入れっぱなしにすると、新聞紙に雑菌が増殖してしまうので注意が必要です。様子を見ながら定期的に新しい新聞紙と交換しましょう。
重曹を使う
重曹は、湿気やにおいを吸収します。日常的ににおい対策をしたい方は、ガーゼまたはストッキング、ティッシュで重曹を包み、輪ゴムで縛ったものを靴に入れておきましょう。
時間が経つと効果がなくなるので、2~3ヶ月ごとに新しいものと交換してください。
また、重曹を靴の中にふりかける方法もあります。次の日までそのままにしておき、重曹をはたき落としてから履いてください。重曹が残るようなら、乾いた布で拭き取りましょう。
靴のにおいを防ぐ方法

靴のにおい対策をするなら、消臭だけでなくにおいを防ぐことが重要です。靴のにおいの予防方法は以下になります。
- ・自身の足に合った靴を履く
- ・清潔な靴下を履く
- ・通気性に優れた靴を履く
- ・靴が濡れたらすぐに乾かす
- ・消臭効果のあるインソールを使う
- ・毎日同じ靴を履かない
- ・靴箱の換気をする
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
自身の足に合った靴を履く
におい対策をするなら、自身の足に合った靴を履きましょう。サイズの合わない靴を履いていると、ストレスを感じて通常よりもにおいの原因となる汗を多くかいてしまいます。
靴のサイズが大きいと靴の中で足がこすれ、雑菌の餌となる角質が剥がれやすくなり、それがにおいの原因となってしまいます。
靴を購入する際には、必ず試着して自身の足に合っているかよく確認しましょう。
清潔な靴下を履く
不衛生な靴下には雑菌が多く付着しています。においが気になる場合には、新しく清潔な靴下を履くと良いです。
靴下の洗濯には除菌・抗菌効果がある洗剤を使いましょう。靴下は裏返しにするのがポイントです。洗濯が終わったら速やかに干しましょう。
普通に洗濯しても靴下のにおいが残る場合には、以下の方法を試してください。
- ・60℃のお湯に約1時間つけてから洗濯する
- ・漂白剤を使って洗濯をする
- ・重曹による漬け置き洗いをする
60℃のお湯につける場合には、靴下が温度に耐えられる素材かを必ずチェックしましょう。
重曹による漬け置き洗いのやり方は、まず洗面器に40℃のお湯のお湯を入れ、大さじ2~3杯の重曹を溶かします。靴下を半日程度つけておき、それから通常どおりの洗濯をしてください。
足に汗をかきやすい方は吸湿性・放湿性に優れた素材の靴下や、5本指ソックスがおすすめです。
素足で靴を履きたい方もいるかもしれませんが、素足で靴を履くと靴下を履いているときより雑菌が多くなるので注意が必要です。
通気性に優れた靴を履く
靴を選ぶ際には、通気性に優れたデザイン、形状の靴を選びましょう。通気性に優れていると靴の中が蒸れにくいので、雑菌があまり繁殖しません。
「パーツに通気口がある」「メッシュ素材を採用」など、通気性の良さを重視した靴も多数販売されているので、その中から自身に合ったものを選ぶと良いでしょう。
革靴の場合には、合成皮革よりも天然皮革のほうが吸湿性・通気性に優れています。デザインや価格だけでなく、素材にも注目して靴を選んでください。
靴が濡れたらすぐに乾かす
もし靴が濡れたら、そのままにせず速やかに乾かしましょう。靴を濡れたまま放置すると、雑菌が増えるだけでなく、カビが生える可能性も高くなります。
濡れた靴は水分を拭き取ってから乾かすと、乾燥時間が短縮できます。自然乾燥させる場合には、直射日光が当たらない、風通しが良い場所を選んでください。
急ぐ場合にはドライヤーで乾かしても良いです。しかし、素材が熱に弱い場合には冷風モードで乾かしてください。布団乾燥機・サーキュレーター・扇風機を使用するのもおすすめです。
靴用のドライヤーには、除菌機能が搭載されているものもあります。革靴・ブーツ・スニーカーなどあらゆる形状の靴に使用できるので便利です。靴が濡れたときだけでなく、日常的に使用すると靴のにおいをしっかり防げるでしょう。
消臭効果のあるインソールを使う
靴を履いているときに、におい対策できるアイテムは、消臭効果のあるインソールです。インソールを使用すると足の裏が直接靴に触れず、汗が染み込みにくくなります。靴を素足で履きたい方は、とくにインソールの使用がおすすめです。
インソールを使用するとフィット感があがり、靴の履きづらさによる発汗も抑えられるでしょう。インソールの種類にもよりますが、使用頻度が高い場合には3~6ヶ月に1度交換しましょう。あまり履かない靴の場合でも、1年に1回を目安に取り替えてください。
毎日同じ靴を履かない
毎日靴を履く方は、日常的に履く靴を最低でも3足用意し、ローテーションで履きましょう。毎日同じ靴を履くと、前日に靴に染み込んだ汗が乾ききらない可能性があります。
湿気を含んだ靴を履いて活動すると、より雑菌が増殖しやすくなります。履いた靴は、2日間休ませると靴の中にこもった湿気を逃がすことができます。
靴箱の換気をする
靴箱は湿気を含んだ靴を収納するため、湿気が溜まりやすいです。靴箱はこまめに換気しましょう。履く頻度が高い靴は、扉のついていない靴箱に収納するのも良い方法です。
靴をしまう場所の湿気が多いと、靴の中が乾かず雑菌が増えてしまいます。梅雨時期はとくに注意が必要です。
靴箱に除湿剤代わりとなる重曹を置くのも1つの方法です。口が広めの容器に重曹を入れ、ガーゼと輪ゴムを使って蓋をしてください。定期的にチェックし、重曹が固まったら取り除き、重曹を補充しましょう。
足のにおいをケアする方法
靴のにおいを防止するためには、足のケアが重要です。足のにおいを軽減するための方法は以下になります。
- ・適切な方法で足を洗う
- ・足の爪を切る
- ・足用の消臭スプレーを使用する
- ・ストレス対策をする
それぞれの方法を詳しく解説します。
適切な方法で足を洗う
足は、抗菌効果のある石鹸を使い、足の裏・指の間・爪の周り・かかとをよく洗いましょう。洗った後は、水分が残らないようタオルでしっかり拭き取るのも大切です。
ゴシゴシと力を入れて洗うと、皮膚が傷つき肌トラブルを起こす可能性が高くなります。手を使って優しく洗いましょう。入り組んだ箇所を洗う際には、フットブラシを使用するのもおすすめです。
足の爪を切る
足の指と爪の間には、足のにおいの原因となる爪垢が溜まります。「爪が長い」「巻き爪」といった状態は、とくに爪垢が溜まりやすいです。足の爪はこまめに切り、巻き爪対策もしましょう。
爪を切る際には、まっすぐ四角くなるように爪を切り、2つの角を丸くする「スクエアオフ」という切り方がおすすめです。爪がサイドに食い込みくにくくなるので、巻き爪の予防になります。
爪垢は取れにくい場所に溜まるので、爪を切るだけでなく意識して除去しなくてはなりません。爪ブラシ・爪垢取りを使用したり、綿棒にクレンジングオイルを染み込ませて拭き取ったりする方法があります。
足用の消臭スプレーを使用する
足のにおいを軽減させるには、足用の消臭スプレーを使用するのがおすすめです。自身に合った消臭スプレーを、つま先を中心とした足裏全体にスプレーしましょう。足の指の間、付け根はとくに丁寧に行うのがポイントです。
すでに汗をかいている場合には、ティッシュで汗を拭き取ってからスプレーしましょう。
ストレス対策をする
ストレスを感じて発汗しやすくなる状態を精神的発汗といいます。汗をかくことで靴がにおいやすくなり、においを感じるとさらにストレスを感じる、といった悪循環に陥りやすい点に気をつけなければなりません。
ストレス対策は、一見足のにおいとは関係なく感じるかもしれません。しかし、適度な運動や趣味を見つけストレスを解消したり、ストレスの要因を避けたりすることは重要です。
気になる靴のにおい対策をしよう
靴のにおいの原因は、足から出る汗や皮脂・靴の通気性の悪さ・靴下の生乾きで起こる雑菌の増殖です。靴のにおいを消すには、靴の洗浄や消臭スプレー・パウダー、新聞紙、重曹を使った方法があります。
また、靴のにおいがきつくなる原因を知り、においを防ぐことも大切です。靴の消臭とともに、靴のにおいを防ぐ方法など、足のケアを実践することでより効果的に靴のにおい対策ができるでしょう。
靴のにおいにストレスを感じている方は、自身に合った方法で消臭・においの予防をしてみてください。