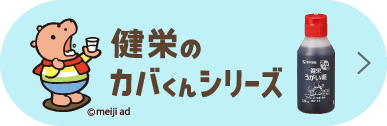妊婦
妊婦はインフルエンザによる重篤な症状や疾患を経験しやすく、インフルエンザの重症度が増す。
妊婦はインフルエンザによる重篤な症状や疾患を経験しやすい。これは、妊娠による身体的変化(呼吸器や細胞性免疫の変化など)が感受性を増大させているかもしれない。2010‒11年および2011‒12年のシーズンに実施された1,873人の妊婦についての研究によると、急性呼吸器疾患のある女性292人においては、インフルエンザ患者は非インフルエンザ患者よりも症状が重かった。また、症例報告や観察研究によって、「妊娠」は入院の必要性および母体の重症合併症を増大させることが示されている。1990‒2002年にカナダのノバスコシア州で実施された妊婦での後ろ向きコホート研究では、134,188人の妊婦の医療記録が妊娠前年の同じ女性の記録と比較された。インフルエンザシーズンの入院率比を妊娠後期と妊娠前年で比較すると、合併症のある女性では7.9、合併症のない女性では5.1であった。
妊婦ではインフルエンザの重症度が増すことは1918‒1919年、1957‒1958年、2009‒2010年のパンデミックのときにも報告されている。分娩後(出産後2週間以内)の女性での重症感染症もまた、2009(H1N1)のパンデミックのときに観察された。2009(H1N1)のパンデミックのときに実施されたケースシリーズでは、集中治療室に入院した280人の妊婦のうち、56人の死亡が報告されている。死亡者のうち、36人(64%)が妊娠後期で発生していた。症状がみられてから4日を経過してから抗ウイルス薬で治療された妊婦は2日以内に治療された妊婦よりも集中治療室への入院が多かった。
胎児
妊婦がインフルエンザに罹患すると、周産期死亡、死産、早産の危険性を増加するという報告はあるものの、それは明確ではない。また、胎児に神経管閉鎖不全、水頭症、心臓および大動脈弁欠損、消化管欠損、口唇裂、肢欠損が引き起こされる危険性が増大するという報告もあるが、そのデータは古い。
1998‒99年シーズンから2001‒02年シーズンまでの620万件以上の妊婦の入院を含む全米入院患者サンプルのデータをレビューすると、インフルエンザシーズンで の呼吸器疾患のある妊婦は呼吸器疾患のない妊婦と比較して、胎児仮死、早期分娩、帝王切開の危険性が増大していた。
2009‒10年のパンデミックのときのノルウェーにおける117,347人の妊婦の研究はインフルエンザを臨床診断された妊婦では胎児死亡の危険性が増大したことを報 告した。英国の221の病院で実施されたコホート研究は2009(H1N1)インフルエンザで入院した女性での周産期死亡、死産、早産の危険性の増加を観察した。しか し、妊娠期間中にインフルエンザが検査確認された女性から生まれた幼児についての他の研究では、非感染女性から生まれた幼児と比較して、早産児、早期分娩、低 体重児、先天異常、低いアプガールスコアの割合が多いことを示さなかった。1985‒86年から1992‒93年のシーズンにテネシーメディケアプログラムに登録された 58,640人の妊婦のコホート研究によって、インフルエンザシーズンに呼吸器入院した妊婦はインフルエンザ入院しなかったコントロール群の妊婦と比較して、早期分 娩、早産児、低体重児の可能性が同程度であることが示された(出産の様式および入院期間もまた両群で同程度であった)。
発熱はインフルエンザの症状としてよくみられるが、これは妊娠期での神経管閉鎖不全およびその他の有害事象と関連しているかもしれない。妊娠早期のインフルエンザ曝露に引き続く先天異常についての22件の観察研究のメタアナリシスによると、妊娠中のインフルエンザは様々な先天異常を引き起こし、それには神経管閉鎖不全、水頭症、心臓および大動脈弁欠損、消化管欠損、口唇裂、肢欠損が含まれている。しかし、それらの研究の多くは1950年代から1970年代に実施されており、 インフルエンザの定義として非特異的なもの(インフルエンザとの報告、インフルエンザ関連疾患、インフルエンザでの発熱、血清学的もしくは臨床的確認の有無な ど)が用いられていた。インフルエンザと先天異常およびその他の出産結果との関係をさらに明らかにするためには追加研究が必要である。
新生児
妊婦にインフルエンザワクチンを接種すると、母体が産生した抗インフルエンザ抗体が胎盤を経由して胎児に移行し、出産後の幼児がインフルエンザから守られる。
不活化インフルエンザワクチンは妊婦に防御レベルの抗体を誘導する。そして、接種された女性から新生児への抗インフルエンザ抗体の受動移動が確認されている。バングラデシュで実施された無作為化比較試験では、妊娠後期の妊婦へのインフルエンザワクチンの接種は肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種した女性と比較して、発熱を伴う呼吸器疾患が36%減少した。さらに、母体のインフルエンザ接種は生後6カ月間の授乳幼児での検査確認インフルエンザの予防において63%の有効性があった。南アフリカでのHIV感染および非感染の女性における3価不活化ワクチンの無作為化プラセボ対照試験はHIV非感染の母親にて50.4%、彼女らの幼児で は48.8%の有効性を報告した。
2000‒2009年の米国の都市の大規模病院に入院した幼児の対症例対照研究は、母体への接種は生後6カ月未満の幼児における検査確認インフルエンザによる入院を かなり低減することを見出した。ネイティブアメリカンにおける前向きコホート研究は接種された母親の生後6カ月未満の幼児は入院および外来において、検査確認 インフルエンザの危険性を41%減少させ、インフルエンザ関連疾患に関連した入院を39%減少させた。生後6カ月未満の1,510人の幼児での研究では、接種された母親の幼児は接種されていない母親の幼児よりも検査確認インフルエンザによる入院は少なかった。
文献
- CDC. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccine s : Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices ̶ United States, 2016 ‒17 Influenza Season
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/pdfs/rr6505.pdf
矢野 邦夫
浜松医療センター 副院長
兼 感染症内科長
兼 臨床研修管理室長
兼 衛生管理室長