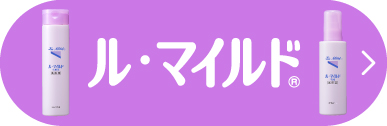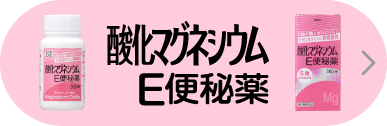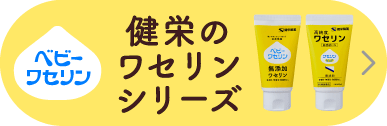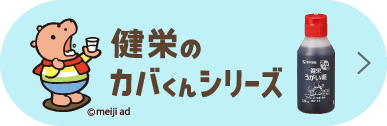コラム
COLUMN

「洗髪やヘアケアをしているのに、フケが目立ってしまう」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
フケには主に乾性フケと脂性フケの2種類があり、原因も頭皮の常在菌やホルモンバランス、ヘアケア方法、生活習慣など人によってさまざまです。
今回は、フケの正体と種類や、フケが出る原因、フケの改善・予防方法をまとめて紹介します。フケに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
フケは「新陳代謝により剥がれ落ちた頭皮の角質層」
フケの正体は、頭皮の古くなった角質が剥がれたものです。新陳代謝により頭皮の表面が剥がれ落ちたものなので誰にでもあります。しかし、フケが増えてくると、髪の毛が汚れて見えたり、衣類についたりして気になってしまう方も多いかもしれません。
フケの量が多いときは、頭皮のトラブルが発生しているかもしれません。放置せず、原因を把握し早めの対処をしましょう。
フケの種類と特徴
フケには、主に脂性フケと乾性フケの2種類があります。
以下では、脂性フケ・乾性フケそれぞれの特徴を詳しく解説するため、自身がどちらに当てはまるかを確認してみましょう。
脂性フケ(ベタベタ)
脂性フケは、頭皮の皮脂の過剰分泌が原因のフケです。脂性フケには、以下のような特徴があります。
- 塊になった湿り気のあるフケ
- 髪の根本付近に貼り付いている
- 湿度が高い梅雨や夏の時期に増える
- 頭皮がベタついていて脂っぽい
とくに、洗髪の頻度が少なめの方や脂っこい食事をする機会が多い方は、脂性フケが出やすい傾向があります。
乾性フケ
乾性フケは、皮脂膜が薄くなり、頭皮が乾燥することに起因するフケです。乾性フケには、以下のような特徴があります。
- パラパラと乾いたフケ
- 肩に落ちているのが目立つ
- 冬などの乾燥した時期に増える
- 成長期の子どもに多い
とくに、洗髪の頻度が多めの方や冬場にフケが気になりやすい方は、乾性フケの可能性が高いでしょう。
フケが出る原因は?
フケが出る原因は、ホルモンやヘアケア習慣、季節、体質などさまざまです。以下では、フケが出やすくなる原因を7つ紹介します。自身がどれに該当するかチェックしてみてください。
ただし、自己判断は難しいため、かゆみや炎症などがひどい場合は早めに医療機関を受診しましょう。
マラセチア真菌の増殖
マラセチア真菌という頭皮の常在菌が増殖すると、フケの原因となる脂漏性皮膚炎を発症することがあります。
脂漏性皮膚炎は、皮脂の分泌が多い部位によく見られる皮膚疾患です。発症すると、フケや皮膚の赤み、かゆみなどの症状が出ます。
脂漏性皮膚炎の原因ははっきりとわかっていませんが、ビタミン類の不足や睡眠不足、ストレスなどが関係すると考えられています。
アンドロゲン(男性ホルモン)の増加
アンドロゲンという男性ホルモンの増加も、フケが増える原因の1つです。アンドロゲンには、頭皮の皮脂分泌を促す作用があり、脂漏性皮膚炎の発症につながります。
アンドロゲンの増加による脂漏性皮膚炎は、とくに思春期以降の男性によく見られる症状です。
洗髪の不足・過剰
洗髪の不足・過剰により、フケが出やすくなっている可能性もあります。
洗髪を1日2回以上する方は、多くても1日1回に抑えることで、乾性フケを予防できるかもしれません。
一方、洗髪頻度が少なく頭皮の皮脂が増えている方は、こまめに洗髪して清潔な状態を保つと、脂性フケを抑えやすくなります。
合わないヘアケア用品の使用
使用中のシャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、ヘアワックス、ヘアスプレーなどの成分が頭皮に合っていない場合も、フケやかゆみの原因となります。
ヘアケア用品を変えてからフケが気になり始めた方は、使用を中止して様子を見るのがおすすめです。また、成分に問題がない場合でも、ヘアケア用品の過剰使用や洗い流し不足によってフケやかゆみが出るケースがあるため注意してください。
季節による乾燥や体質
頭皮の乾燥は、もともとの体質や環境も大きく影響します。例えば、アトピー性皮膚炎などが原因でフケが増えることも珍しくありません。
また、冬は肌と同じように頭皮も乾燥しやすくなります。暖房や乾燥した外気にさらされることで乾性フケが出る場合もあるため注意しましょう。
生活習慣の乱れ
不規則な生活をしていると、頭皮が荒れてフケの原因となることがあります。
とくに、肌細胞の修復に必要な成長ホルモンが分泌される午後10時~午前2時は眠るようにし、睡眠時間を十分に確保してください。
また、偏った食生活も頭皮に悪影響を与える可能性があります。乾性フケが気になる方は、ビタミンB2を積極的に摂取しましょう。
ビタミンB2が不足すると、肌荒れや髪のトラブルが起きやすくなります。ビタミンB2はレバーや牛乳、納豆などに多く含まれているため、食事に取り入れてみてください。
そのほか、ストレスによるホルモンバランスの乱れがフケの原因となることもあります。
フケが気になるときは、適度に運動したり好きなことをする時間を作ったりして、ストレスを発散すると良いでしょう。
紫外線
外に出ると避けられない紫外線も、頭皮にダメージを与える要因の1つです。
夏の強い紫外線を長時間浴びると、毛が日焼けして茶色く変色するのを経験したことがある方もいるのではないでしょうか。
毛で被われているといえ、頭皮も日焼けして赤く炎症を伴います。その後、炎症した角質は次々と剥がれ落ちてフケになるのです。
気になるフケを予防・改善するためのポイント

頑固なフケも、生活習慣の工夫により改善・予防が可能です。最後に、フケ改善・予防に役立つポイントを4つ紹介します。
髪の洗い方を見直す
シャワーを浴びるときは、38~40℃のぬるめのお湯を使いましょう。高温のシャワーやドライヤーの熱は、頭皮を乾燥させる原因となります。
また、ドライヤーの熱は、100℃近くまで上昇することもあり、頭皮に近づけると水分を蒸発させてしまいます。ドライヤーを使うときは、頭皮に近づけすぎないよう注意してください。
規則正しい生活を意識する
規則正しい生活を送ることも大切です。頭皮のターンオーバーを整えるには、タンパク質やビタミン、ミネラルを中心としたバランスの良い食事を心がけてください。
睡眠を十分に取り、趣味や好きなことをしてストレスを発散するのも良いでしょう。
頭皮をマッサージする
疲れや肩こりの影響で頭の筋肉が収縮すると、頭皮の血流が悪くなりフケの原因になります。
頭皮のセルフマッサージは、以下のような手順で行いましょう。
- 耳の後ろの皮膚を、円を描くように動かす
- 頭皮を上方向に引き上げる
- 頭皮を頭頂部の方向に押し集める
- 両手で頭全体を包むようにして、頭皮全体を上方向に引き上げる
乾性フケの方は、マッサージオイルを使用するのもおすすめです。
乾性フケの場合は乾燥肌治療薬を使用する
カサカサした乾性フケが多い方は、ヘパリン類似物質などの治療薬を使用するのも効果的です。
ヘパリン類似物質が含まれた医薬品は、クリームタイプやローションタイプなど複数の種類があり、保湿・血行促進・抗炎症作用が期待できます。
なかでもスプレータイプは逆さにしても使えるため、頭皮にさっと吹きかけられて便利です。
なお、健栄製薬のオンラインショップでも取り扱っているため、ぜひ利用を検討してみてください。
https://kenei-online.shop/collections/healmild
フケの原因を知って、適切に対策しよう
フケとは、頭皮の古くなった角質が剥がれたもので、主に脂性フケと乾性フケの2種類に区分されます。フケが出る原因は、頭皮の常在菌やホルモンバランス、ヘアケア習慣、生活習慣など、人によってさまざまです。
フケが気になる方は、今回の内容を参考に、適切な対策を行いましょう。長期間フケに悩んでいる方も、生活習慣に工夫を取り入れることで、症状が改善する可能性があります。
ただし、セルフケアで改善が見られないときは、皮膚科の受診も検討しましょう。

このコラムが気に入ったらシェアしよう!
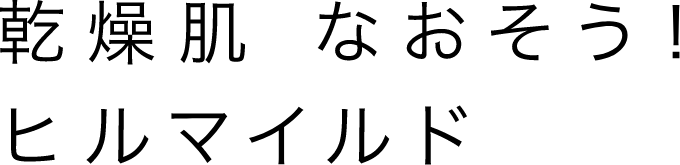
乾燥肌治療薬
-
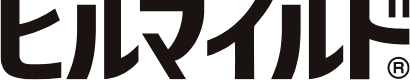
第2類医薬品
- クリーム
- ローション
- スプレー
- Hクリーム
- 泡フォーム