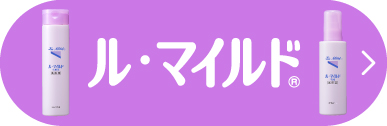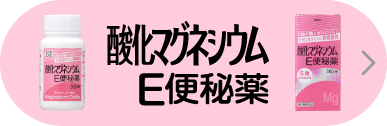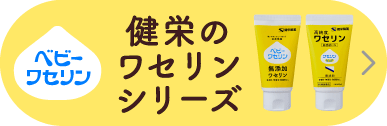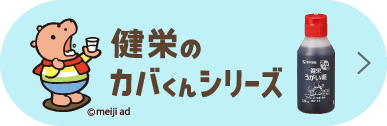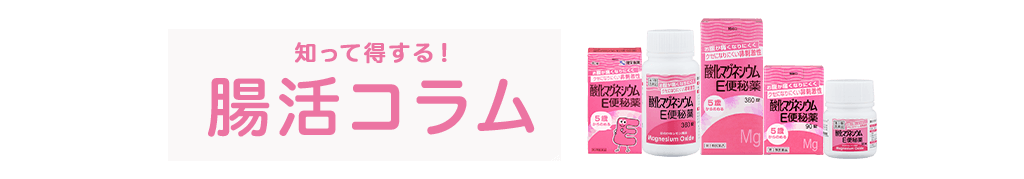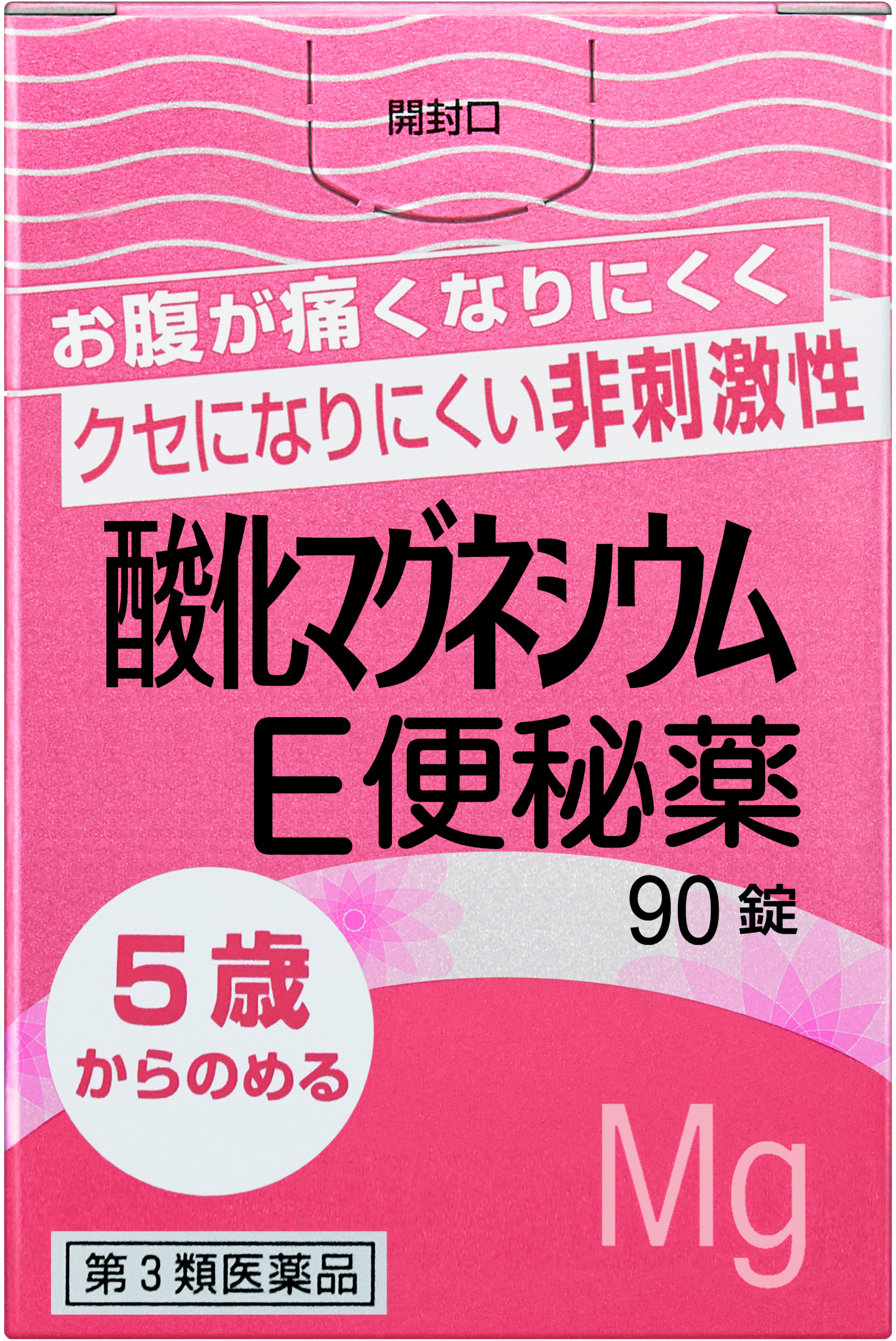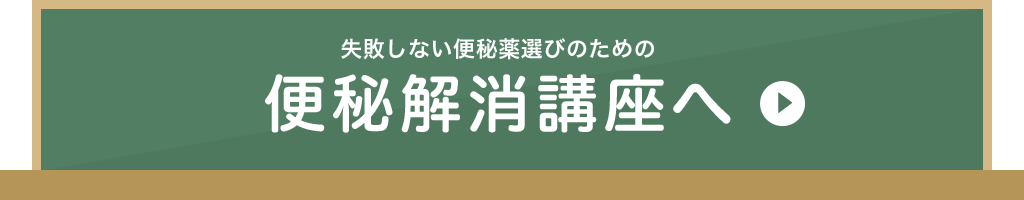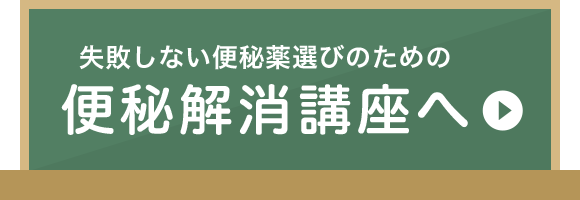VOL.81 便意があるのに出ないときの対処法4選!便秘の原因と予防方法も解説

便意を催してトイレに座っても、なかなか排便できず不快に感じている方も多いでしょう。便意があるのに出ないのは、便が肛門付近に溜まっているにもかかわらず、出口で詰まっている状態です。
今回は、便意があるのに出ないのはどのような状態なのかを解説した上で、便秘の原因や自宅ですぐに試せる対処法、長期的に見た便秘の改善・予防方法もあわせて紹介します。
便が出ない不快感を早めに解消したい方は、ぜひ参考にしてください。
便意があるのに出ないのはどんな状態?
便意があるのに出ないのは、便が出口(肛門付近)まで来ているにもかかわらず、出口で詰まって出てくれない状態です。便が肛門付近で詰まる状態は、便秘と考えられます。
「便通異常症診療ガイドライン2023」(編集:日本消化管学会)では、便秘を以下のように定義しています。
| 本来排泄すべき便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排泄回数の減少や、便を快適に排泄できないことによる過度の怒責、残便感、直腸肛門の閉塞感さらに用手的排便介助の必要性といった排便困難に関連する症状などを慢性的に認める状態 |
便秘を発症すると、排便がしにくくなる以外に、腹痛やおなら、お腹の張りなどの症状が出ることも珍しくありません。排便時に硬くコロコロした便が少しだけ出たり、排便後に残便感が残ったりする場合もあります。
また、にきび・肌荒れといった肌トラブルや、頭痛・肩こりを併発するケースも多いため注意が必要です。
なお、便意があるのに出ない便秘の原因を以下で紹介しますが、大腸がんなどといった重大な病気の可能性もあるため、便秘の症状が続くなど、心配な方は医療機関への相談もご検討ください。
便秘になる原因(がんなどの重大な病気を除く)
便秘の原因は多岐に渡りますが、ここでは大腸がんや手術した後の大腸など、重大な病気ではない場合の便秘について、3つの主な要因を紹介していきます。
栄養・水分不足
腸の動きそのものには問題がなくても、偏った食生活や栄養摂食量の不足によって便秘が引き起こされることがあります。
例えば、ダイエットで食事量を減らしている方や、高齢で食事量が少なくなってきた方の場合、便のもとになる食物の量が減るため、便秘になりやすくなります。
とくに、食物繊維は排便するために欠かせない栄養素です。しかし、食物繊維ばかりを食べて炭水化物やタンパク質、脂質などの摂取を控えると、栄養が偏りかえって便秘が悪化してしまう可能性があります。
便秘改善を目指すなら、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
また、便の6~8割ほどは水分で構成されており、体内の水分が不足すると、便が硬くなったり便が作られにくくなったりするため注意が必要です。
腸の動きの低下
腸のぜん動運動が低下すると、排便回数や排便量が減少し、便秘になりやすくなります。
ぜん動運動とは、腸管の口側が収縮し、肛門側が弛緩することで、腸の内容物を先へ押し出す運動のことです。ぜん動運動が鈍くなると、腸管内の内容物を十分に押し出せず、便が滞留しやすくなります。
ストレス
腸の働きは、自律神経によってバランスが保たれています。自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、交感神経が腸の動きを抑制し、副交感神経が腸の動きを促進する仕組みです。
ストレスや疲労が蓄積すると、自律神経が乱れて腸が正常に動かなくなり、便秘を発症しやすくなります。
環境の変化や多忙などのストレスが原因で便秘が起きている方の場合、ストレスの原因を取り除くことで、便秘が改善するケースも少なくありません。
便意があるのに出ないときの対処法4選

次に、便意があるのに出ないときに、すぐに実践できる対処法を4つ紹介します。つらい便秘を早めに解消したい方は、ぜひできるものから試してみてください。
①排便時の姿勢を変える
排便時の姿勢を変えることで、肛門付近に溜まった便が出やすくなる可能性があります。排便時は、背筋を伸ばした前屈みの姿勢を意識してみましょう。姿勢が起きた状態や背中が丸まった状態でいきんでも、肛門に力が伝わりにくいため注意が必要です。
また、子どもや身長が低い方など、便器に座った際に足が床から離れている方は、足元に台を置いて膝の位置を上げることで、排便しやすくなるケースもあります。直腸が肛門に対して真っ直ぐに近づき、便が出やすくなる効果があります。
②腸をマッサージする
腸を軽く叩いたり揉んだりしてマッサージすることで、腸の動きが活発化し、排便できることもあります。マッサージ方法はいくつかありますが、一例として、便器に座りながらできるマッサージの手順は以下のとおりです。
- 1. 便器に座ったまま、両手のひらで腰背部をリズミカルにさする
- 2. 同様に脇腹をさする
- 3. 同様にお腹の前面をさする
トイレ以外の場所で行うときは、仰向けに寝てお腹の上を、円を描くようにさすったり、軽くトントンと叩いたりする方法もおすすめです。
③浣腸を使用する
浣腸は、肛門から腸内に液体を注入することで、排便を促す薬剤です。即効性が高く、つらい便秘を早めに解消したいときに効果を発揮します。
なお、使用時は製品記載の注意事項をよく読み、適切な方法で注入を行いましょう。
浣腸について詳しくは以下のコラムもご覧ください。
【医師監修】浣腸の仕組みとは?使うタイミングや適切な使い方を解説
④酸化マグネシウム便秘薬を服用する
便秘解消には、酸化マグネシウム便秘薬の服用も効果的です。酸化マグネシウム便秘薬は、お腹が痛くなりにくくクセにもなりにくい薬剤で、浣腸と比べるとゆるやかに排便を促せます。
酸化マグネシウム便秘薬の服用から効果が現れるまでの時間は、8~12時間程度です。ただし腸の状態によっては、効果が現れるまでに1日から数日程度かかる場合もあります。
また、酸化マグネシウム便秘薬は、就寝前または空腹時に水やぬるま湯で服用してください。就寝前に服用すると、翌朝にちょうどよく排便しやすくなります。
なお、酸化マグネシウム便秘薬は健栄製薬のオンラインショップでも購入できるため、気になる方はぜひ検討してみてください。
https://kenei-online.shop/collections/ebenpi
生活習慣で変わる!便秘の改善・予防方法
大腸ガンなどの器質的な病気を除き、便秘を改善するためには生活習慣を見直す必要があります。
以下では、日頃からできる便秘の改善・予防方法を4つ紹介していきます。
栄養バランスのとれた食事を心がける
便秘を予防するには、普段から栄養バランスの整った食事を心がけることが大切です。
便秘を改善するには、とくに食物繊維が大事だといわれています。食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があるため、両方をバランス良く摂取しましょう。
水溶性食物繊維は水に溶けて腸内細菌(善玉菌)の栄養になり、不溶性食物繊維は水分を吸収して便をやわらかくし、便の量を増やしてくれます。不溶性食物繊維を水分とともに摂ると、便に留まる水分量が増えて、やわらかい便を形成しやすくなります。
また、食物繊維だけでなく、糖質、タンパク質、脂質も適切な量を摂ることが重要です。
豊富な栄養を摂取して便の量が増えれば、腸管の動きが活発になり、便意が起きやすくなります。
不溶性食物繊維や糖質、タンパク質、脂質を含む食品の例は、以下のとおりです。
| 項目 | 食品の例 |
| 不溶性食物繊維を含む食品 | きのこ、豆類、穀類、野菜類 |
| 糖質を含む食品 | 穀類、いも類、かぼちゃ、とうもろこし |
| タンパク質を含む食品 | 大豆・大豆製品、肉類、魚類、牛乳・乳製品、卵類 |
| 脂質を含む食品 | 肉類、魚類、乳製品、バター、植物油、魚油 |
食事メニューを考える際は、含まれる栄養素にも注目して、食材を選んでみてください。
水分をしっかり摂る
便秘を改善するには、水分をこまめに摂ることが大切です。
ただし、一度に大量の水分を摂っても、尿として体外に出る量が増えるだけで、便秘予防効果はあまり期待できません。
便秘予防の目的で水分を摂取するときは、毎回の食事に汁物を足す、食事中や食後にお茶を飲むなどの方法で、摂取回数を増やすことを意識してみましょう。
適度に運動する
先述のとおり、自律神経の乱れが便秘を発症させる可能性があります。適度に運動することで、自律神経を整えることができます。
例えば、ウォーキングやストレッチなどの軽めの運動をすることで、排便を促す副交感神経を刺激できます。日頃運動不足だと感じる方は、できる範囲の運動からはじめてみましょう。
規則正しい生活を送る
規則正しい生活を送ることも、便秘予防に効果的です。便秘が気になるときは十分な睡眠時間を確保し、決まった時間に食事を摂ったり、お風呂に入ってリラックスしたりして、自律神経を整えましょう。
また、決まった時間にトイレに行く習慣をつけるのもおすすめです。毎朝トイレに行く時間を決めておけば、体に排便リズムが定着し、決まった時間に排泄しやすくなります。
便秘解消方法を試して、すっきりとした排便を目指そう
便秘は腹部膨満感や腹痛、残便感などの不快感を伴います。不快感に悩まされないためにも、便秘になってから対処するのではなく、日頃から便秘を予防することが大切です。今回紹介した予防方法を、実践できるものから試してみてください。
どうしても便が出ないときや便が硬くて出しにくいときは、市販の酸化マグネシウム便秘薬や浣腸を試してみるのも良いでしょう。
とくに、酸化マグネシウム便秘薬は、8〜12時間程度かけてゆるやかに排便を促すため、就寝前に服用すれば、翌朝に快適に排便できる可能性もあります。