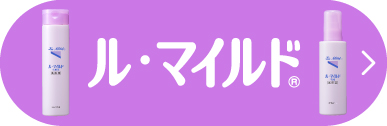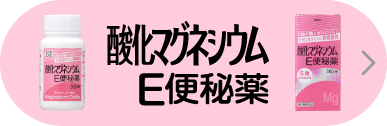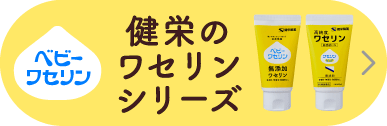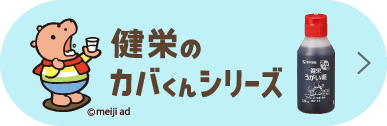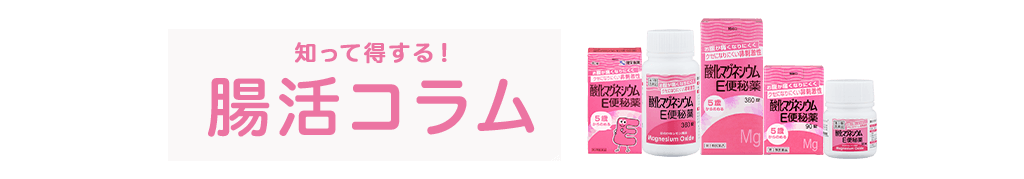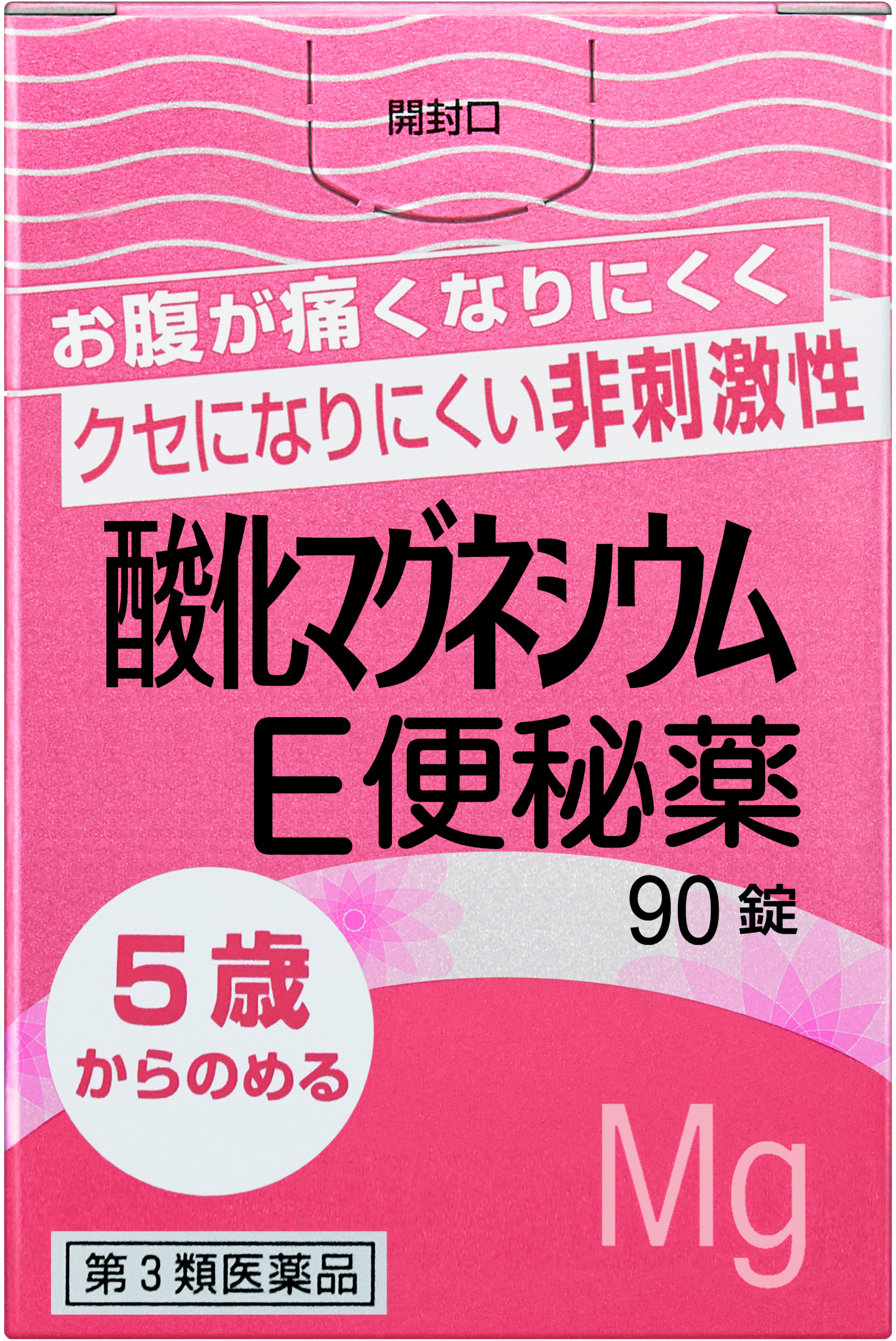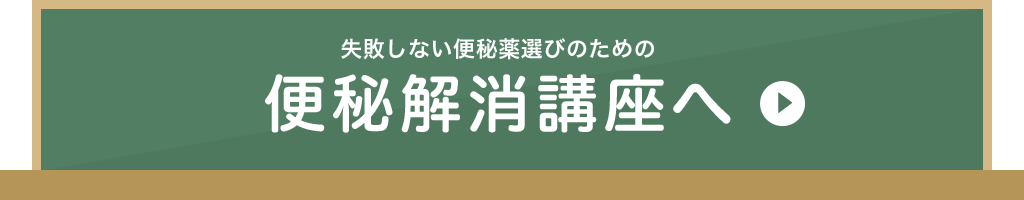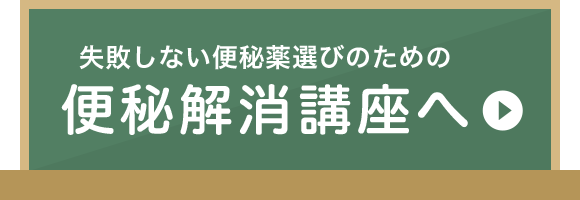VOL.17 赤ちゃんが便秘になったらどうする?なりやすい時期や予防・改善方法を紹介

赤ちゃんの健康を保つためには、食事や睡眠だけでなく、お通じも大事なポイントになります。
赤ちゃんは自身で便秘の症状を伝えることができないので、便秘になっていないかどうか、親がしっかりと見てあげなくてはいけません。
そのためには、便秘かどうかの判断基準や便秘になりやすい時期、便秘になったときの適切な対処法を知っておく必要があります。
そこで今回は、赤ちゃんの便秘について、その特徴や対処法を紹介します。
赤ちゃんが便秘かどうかの判断とは
赤ちゃんの便はやわらかいですが、便秘になることも少なくありません。
しかし、赤ちゃんは便秘になっても言葉で伝えられないため、大人が様子を見て気づいてあげる必要があります。以下のような症状が見られたら、便秘の可能性があると考えられます。
- ●うんちの回数が減っている
- ●母乳を飲みたがらない、吐き戻す
- ●赤ちゃんの機嫌が悪い
- ●うんちの量が少ない、硬い
赤ちゃんが便秘になる原因
赤ちゃんが便秘になる原因には、主に以下があります。
- ●便の形状が不安定
- ●排便のペースが不規則
- ●排便のためにいきむ力が弱い
- ●水分不足
赤ちゃんは、腸などの消化器官が未発達なため、便の形状や排便のペースが安定しにくいです。筋肉量も少ないので便を出そうといきむ力が弱く、便秘を起こしやすいといわれています。
また、一般的な便秘の原因と同様に、水分が足りないせいで便秘になる赤ちゃんもいます。
赤ちゃんが便秘になりやすい時期
赤ちゃんは、成長とともに便の形状や排便のペースも変化していきます。消化器官の発達や食事内容の変化に伴い、便秘の原因も変わります。
生後6ヶ月頃までの赤ちゃんの便秘の特徴や原因について、「新生児期」、「生後2~3ヶ月頃」、「生後5~6ヶ月頃」の3つに分けて見ていきましょう。
新生児期
生まれたばかりの赤ちゃんが便秘になることは稀です。成長とともに腸が発達し、授乳回数が減少することで排便のペースが変化し、便の回数が減っていきますが、自然な現象と考えて問題ありません。
ただし、母乳やミルクの摂取量が足りないことで便秘になるケースもあります。体重をチェックし母乳やミルクが十分摂取できているかチェックしましょう。
なお、完全ミルクの場合は消化に時間がかかるため、母乳を飲む赤ちゃんよりも便秘になりやすい傾向があるようです。
生後2、3ヶ月頃
消化器官がある程度発達したことによって、腸内に便を溜めることができるようになる時期です。そのため、便がお腹に留まり出にくくなる赤ちゃんもいるようです。
離乳食を始めた頃(生後5、6ヶ月頃)
赤ちゃんがとくに便秘になりやすい時期です。離乳食を始めると、授乳のみだった頃より水分の摂取量が減少します。
また、大腸の発達により水分が吸収されやすくなるため、便が固まりやすくなります。
固い便によって切れ痔を起こしてしまうと、その痛みを恐れて排便を我慢し、その結果便秘を引き起こすこともあるようです。
赤ちゃんがなりやすい「ディスケジア(乳児排便困難症)」とは
赤ちゃんは、排便のためにタイミング良くいきんだり肛門をゆるめたりすることがまだ難しいため、便が出せないことがあります。便はやわらかいものの、排便のための協調運動(腹圧をかける、肛門をゆるめる)がうまくできないのです。
排便のための協調運動が未熟なせいで便が出にくい状態は、ディスケジア(乳児排便困難症)と呼ばれ、厳密には便秘とは区別されます。
生後9ヶ月未満の赤ちゃんに起こりやすいもので、出た便がやわらかければ便秘ではありません。
一般的には、排便のための協調運動を自然と習得していき、3~4週間程度で改善されるため治療は不要です。
病院を受診する判断基準
赤ちゃんの排便ペースは不安定なので、少しの期間便が出なかったからといって過剰な心配をする必要はありません。
病院を受診するかどうかは、便が出ない期間で決めるのではなく、赤ちゃんの様子を見て判断することが大切です。
もしも、次のような症状が見られる場合は、すぐに病院を受診するようにしてください。重度の便秘や、腸の形状(もしくは機能)の異常、何らかの病気である可能性が考えられます。
- ●ぐったりしていて熱がある
- ●お腹がパンパンに張っている
- ●排便時に出血がある
- ●血便が出る
- ●嘔吐を繰り返す
- ●緑色の嘔吐がみられる
- ●1週間以上の便秘が何度も続く
すぐにできる赤ちゃんの便秘対処法

便秘が疑われる場合で、体調や食欲には大きな変化が見られないときは、まずは家庭での対処法を試してみましょう。
簡単ですぐにできる便秘対処法を紹介します。
お腹のマッサージ
運動不足による便秘の場合は、マッサージが効果的です。おへそを中心に、お腹に「の」の字を書くように優しくさすってあげてください。
ほかにも、赤ちゃんの両足を持って、自転車を漕ぐようなイメージで交互にゆっくりと動かす運動もおすすめです。
綿棒で肛門を刺激
お尻に刺激を与えて排便を促す方法です。まずは綿棒にミネラルオイルやワセリンを塗り、肛門から1cmほど挿入します。
ゆっくりと回すように10秒ほど綿棒を動かしましょう。あまり強く刺激しないように注意してください。
ただし、綿棒による刺激で排便を促すことを習慣化すると、自力での排便が妨げられてしまいます。
あくまでも、赤ちゃんが苦しそうなときに便を出してあげるための応急処置として用いましょう。習慣的には使わないようにしましょう。
赤ちゃんの便秘の予防・改善方法
日頃から赤ちゃんの便秘を予防・改善するために、日常生活の中でできることを紹介します。
食事・睡眠の時間を決める
ミルクや離乳食はなるべく決まった時間に与え、生活リズムを整えるようにしましょう。
また、夜寝かせる時間も決めると、自律神経の働きを整える効果が期待できます。自律神経は排便リズムをコントロールしているので、これを整えることで便秘も解消できると考えられます。
水分を摂る
離乳食を食べ始めた赤ちゃんは、母乳やミルクが減った分だけ水分が不足してしまいがちです。白湯やお茶で、不足した水分を補うように意識してください。
離乳食に便秘改善の食材をプラスする
離乳食を開始している赤ちゃんには、食物繊維が豊富な食事を与えるようにしましょう。
例えば、さつまいものペーストや、すりおろしたりんごなどは、便秘の解消が期待できるメニューです。
また、ヨーグルトも毎日少しずつ食べさせると、お通じが良くなる可能性があります。
腹ばいで腹筋を鍛える
生後2ヶ月頃からを目安に、赤ちゃんを腹ばいにする時間を作りましょう。
腹ばいは、赤ちゃんをうつ伏せにして顔を上げた状態です。腹筋を使う体勢のため、便秘の解消や予防に役立ちます。さらに、運動能力や呼吸機能の発達を促す効果も期待できます。
赤ちゃんを腹ばいにする際には、窒息予防のため必ず大人が見守るようにしてください。体が沈んだり顔が埋もれたりしない硬さの場所で行いましょう。
便の記録を取る
赤ちゃんの排便には個人差があるため、便秘かどうか家庭で判断するのが難しいケースも多いです。
そこで、日頃から便について記録する習慣をつけると、判断や対処がしやすくなります。
通常時の便の形状や色、回数を記録すると、異変があった際にわかりやすいです。母子手帳に付属している便色カードを活用するのも良いでしょう。受診の際に記録を持参すれば、医師に状態をわかりやすく伝えるためにも役立てられます。
赤ちゃんの便秘に市販薬は使える?
赤ちゃんの便秘で受診した場合、便秘薬ではなく整腸剤が処方されることもあります。症状によっては、病院で処方された整腸剤のみで便秘が改善するかもしれません。
乳児用の便秘薬は、医療機関で処方されるほか、ドラッグストアなどでも購入可能です。赤ちゃんに使える便秘薬は、体に負担をかけない成分で作られています。麦芽糖(マルトース)、ラクツロースなどが主成分のものが多いです。
便秘薬は年齢によって使用できる種類が異なるため、購入前に必ず対象年齢などの記載内容を確認しましょう。なお、用法容量を守って適切に使用してください。
5歳以上の子どもは、健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」も使用できます。オンラインショップでも購入でき、お腹が痛くなりにくく、クセになりにくい便秘薬です。お子さんが5歳以上になったら購入を検討してみてください。
https://kenei-online.shop/collections/ebenpi
赤ちゃんの便秘は期間ではなく、お子さんの様子を見て判断・対処しよう
赤ちゃんは腸の発達や排便に必要な力が未熟なため、便の形状や回数が不安定です。
また、成長に伴う体や食事の変化からも影響を受けやすいため、一時的に便秘になったり、便秘に似たような状態が見られたりすることも少なくありません。さらに、個人差もあるため、判断が難しく悩む方もいるでしょう。
赤ちゃんの便秘が疑われる場合は、排便のない期間ではなく、お子さんの様子を観察することが大切です。
その上で対処法を試す、受診する、市販の便秘薬を使用するなど、状態に合わせて判断・対処することが望ましいです。加えて、日頃から便秘を予防・改善する方法を取り入れながら生活しましょう。