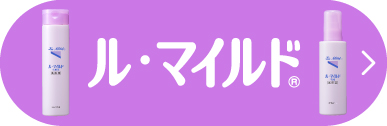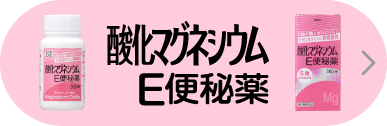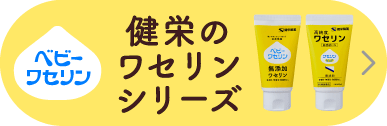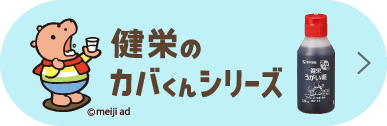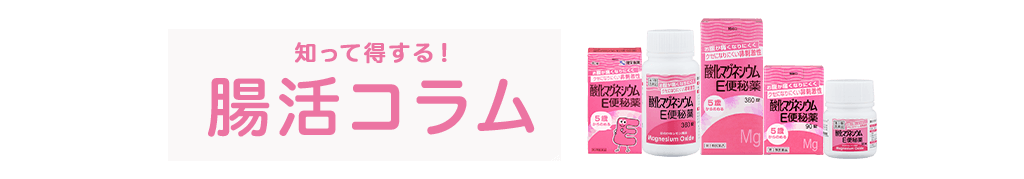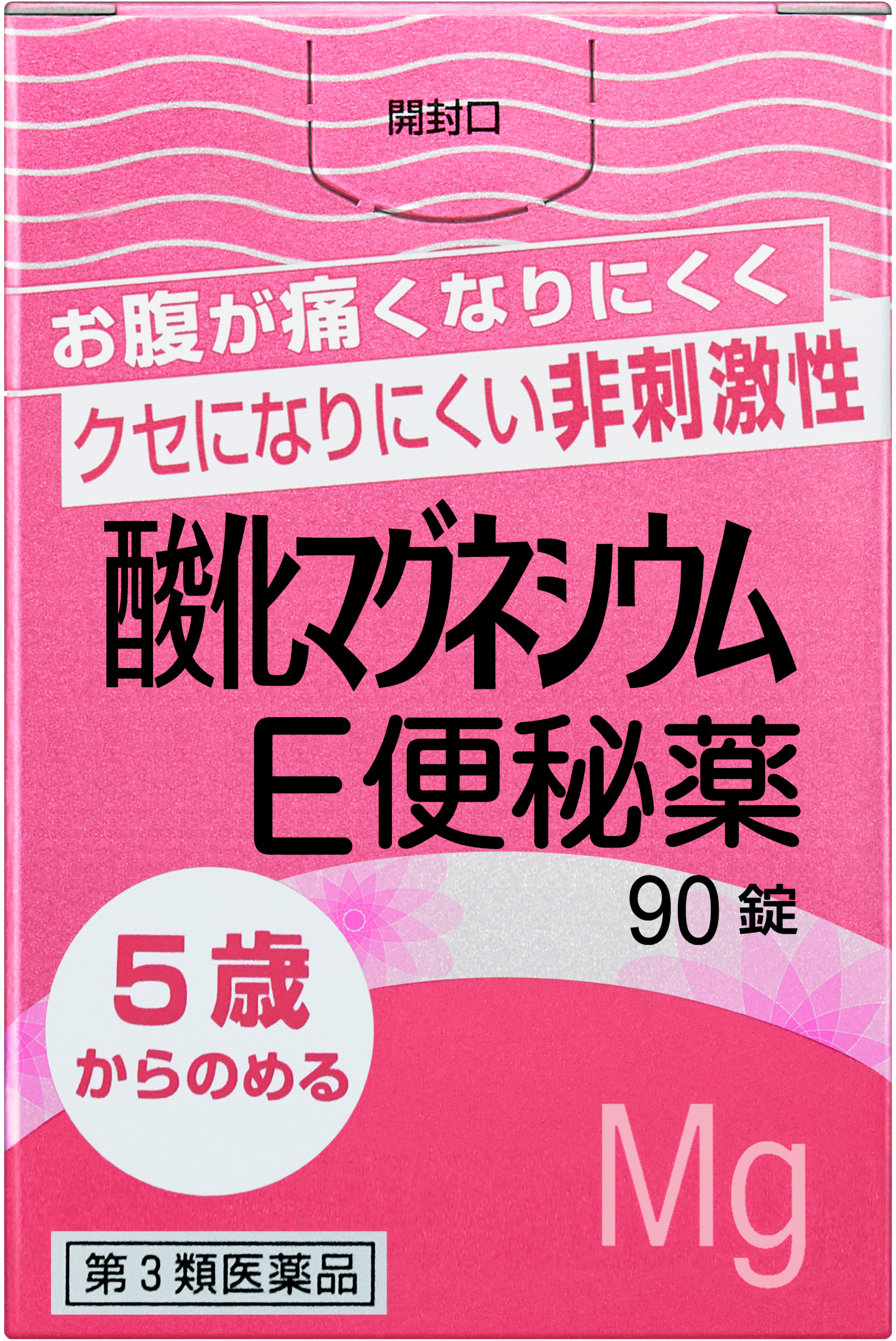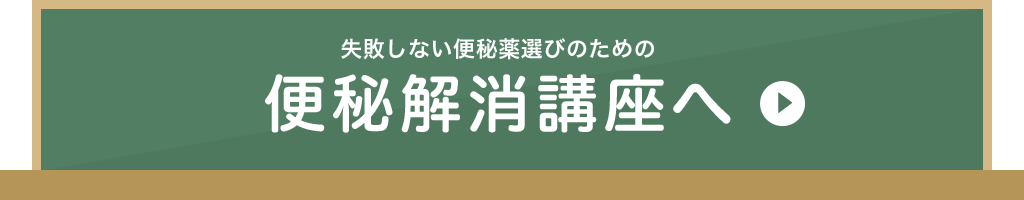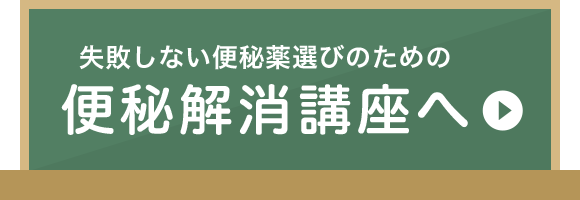VOL.147 健康な方の排便回数は?便の状態での体調の見分け方と異常時の対処法

排便回数が人より多い・少ないと感じた場合、どこか体に異常があるのかと気になる方も多いのではないでしょうか。
排便回数には個人差がありますが、多すぎる・少なすぎる場合は感染症や疾患が隠れている可能性もあるため注意が必要です。
今回は、正常な排便回数の目安と、便で健康状態を見分ける方法を解説します。なお、便秘が続く際は生活習慣に問題があるケースもあるため、特筆した原因がないのに便秘が治らないときは、食生活や運動習慣などを見直してみるのも1つの方法です。
自身の排便回数は多い?少ない?健康な方の排便回数をチェック
通常、健康な方の排便回数は1日1〜2回程度です。しかし排便回数には個人差があり、1日3回から1週間に3回程度であれば正常の範囲内と考えられます。
なお、排便回数が1日に5回以上、1週間に1〜2回以下の状態が続く場合、下痢症・便秘症の可能性があるため、一度医療機関に相談してみてください。
排便回数以外にも!便の状態からわかる体調の変化
排便回数以外でも、便の状態からはさまざまな体調の変化を読み取ることができます。
以下では、便の状態と体調の関係を「性状」「におい」「量」「色」の4つのポイントに分けて見ていきましょう。
便の性状
硬さや形といった便の性状からわかる体調変化の目安は、以下のとおりです。
- ・バナナ状または半練り状・においが少なくスムーズに排便できる:健康な便
- ・ウサギの糞状のコロコロした硬い便:腸内の悪玉菌が優位で便秘気味の状態
- ・ドロまたは水のような水分の多い便:下痢気味。便に血液や粘液、膿が混じっている場合は、アレルギー性の下痢や細菌性赤痢、伝染性下痢の可能性がある
- ・硬い便と水分の多い便が交互に出る:便秘と下痢を交互に繰り返している状態
便秘や下痢の原因は、人によってさまざまです。ひどい便秘や下痢が続く場合、便に血液や粘液、膿が混じっている場合などは、早めに医療機関を受診しましょう。
便のにおい
便のにおいの原因は、腸内細菌がタンパク質を分解するときにできるスカトール・インドールという物質です。
便秘で便が腸内に長く滞留したときや腸に疾患があるとき、腸の働きが弱っているときは、便のにおいが強くなる傾向があります。便のにおいが通常より強いと感じたときは、医療機関に相談すると良いでしょう。
ただし、肉やチーズ、ジャンクフードなどを食べた場合も便がにおいやすくなるため、便のにおいが強くなった場合は、食事内容が原因の可能性もあります。食事内容が原因と考えられる場合、におい以外でとくに異常がなければ、これを機に食生活の見直しをすると良いかもしれません。
便の量
便の量は食事量や食事内容によって異なり、植物性の食品を多く食べる方は量が多く、肉類を多く食べる方は量が少なくなる傾向があります。
便の量の目安は1日平均100〜200g程度です。目視で確認する場合、バナナ1.5~2本分の量を目安とすると良いでしょう。
なお、1日に100〜200g程度の便が出なくても、先述のとおり1日3回から1週間に3回程度排便ができていれば、正常の範囲内と考えられます。
便の色
便の色からわかる体調変化の目安は、以下のとおりです。
- ・黄褐色:健康な状態
- ・茶色・茶褐色:食べすぎ・飲みすぎが疑われる状態
- ・黄:下痢気味
- ・濃褐色:便秘気味、または肉類の多い食事を多量摂取した状態。ココアやチョコレートの摂取でも濃褐色の便が見られることがある
- ・黒色(タール便):上部消化管からの出血が疑われる状態。1,000ml以上の出血があると、2〜3日連続で黒色の便が出ることがある。またイカ墨料理や鉄剤、薬用炭、ビスマス剤などを摂取した場合にも黒色の便が見られることがある
- ・緑色:急性腸炎や消化不良が疑われる状態。クロロフィルを含む緑黄色野菜を多量摂取した場合も、緑色の便が見られることがある
- ・赤色:大腸がんを含む大腸疾患や痔が疑われる状態。出血場所が肛門に近いほど、鮮やかな赤色になる
- ・灰白色:肝障害や腸結核、膵臓疾患などが疑われる状態。バリウムを飲んだ後にも灰白色の便が見られることがある
- ・乳白色:コレラや、乳幼児の場合はロタウイルスへの感染が疑われる状態
- ・ゼリー状の赤色:アメーバ赤痢への感染が疑われる状態
便の色は、体調の変化だけでなく食事内容や服用中の薬の影響を受けることもあるため、気になる場合は医師に相談しましょう。
また、食事内容や薬の服用などの心当たりがないにもかかわらず黒色や緑色、赤色、灰白色といった通常と異なる色の便が出る場合、疾患の可能性があるため、できるだけ早く医療機関を受診してください。
排便回数や便の状態がおかしいと感じたときの対処法

排便回数や便の状態に異常がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。下痢・便秘が続く場合や普段と違うにおい、色などの異変が見られるときは、感染症や疾患が隠れている可能性があります。
なお、慢性的な便秘は生活習慣の乱れに起因する場合があり、生活習慣を変えることで改善することも考えられます。便秘が続く際は、以降で紹介する生活習慣の改善も検討してみてください。
日常でできる便秘の解消・予防方法
以下では、日常でできる便秘の解消方法・予防方法を解説します。
ただし、以下の方法を試しても便秘が改善しない場合は、様子を見すぎずに、早めに医療機関を受診しましょう。
水分を多めに摂取する
便秘が気になるときは、水分を多めに摂取してください。水分が少なく硬い便は排出しにくく、便秘につながりやすいためです。
水分は、1日2リットルを目安に摂取しましょう。利尿作用のある緑茶やコーヒー、紅茶よりも、水やお湯、麦茶などを飲むのがおすすめです。
適度に運動する
運動不足になりやすい方は、適度な運動習慣を取り入れることもポイントです。適度な運動には、腸のぜん動運動を促す効果が期待できます。
運動をするときは、まずウォーキングやジョギング、水泳などの全身運動や、腹筋運動を試すと良いでしょう。腹部の筋肉を鍛えれば、腸の動きや排便をサポートしてくれます。
また、あおむけに寝てお腹を「の」の字にマッサージする方法も有効です。
食物繊維の豊富な食事を摂る
普段から規則正しい食事を摂り、食物繊維も意識的に摂取しましょう。食物繊維には、便を柔らかくし、かさを増やして排便しやすくする効果があります。加えて、腸内の善玉菌の餌になったり、便の形を整えたりする効果も期待できます。
便秘が続く場合は、食物繊維が多く含まれる穀物や芋類、果物、生野菜、きのこ類、藻類などの食材を多めに摂取してみてください。
酸化マグネシウム便秘薬を服用する
酸化マグネシウム便秘薬の服用も検討すると良いでしょう。酸化マグネシウム便秘薬は、便を柔らかくして排泄しやすくする効果が期待できる薬剤です。
効果の現れ方は比較的ゆるやかで、大量の水と一緒に服用すると、1〜2時間程度で便意を催す傾向があります。クセになりにくく、服用後にお腹が痛くなりにくいこともメリットです。
ただし、ほかの薬を服用している方や持病がある方は、服用しても問題ないか医師に相談してから、用法用量を守って使用してください。
浣腸を使用する
頑固な便秘に悩んでいる方は、浣腸を使用するのも1つの方法です。浣腸は、肛門から薬液を注入し、腸管を刺激して排便を促す薬剤です。
酸化マグネシウム便秘薬よりも即効性があり、使用後数分程度で便意を催すため、忙しい時間帯を避けて自身に都合の良いタイミングで排便ができます。
浣腸はクセになりにくい薬剤ですが、常用は避けましょう。また、痔や腸出血がある方は使用できないほか、妊娠中・授乳中の方や持病がある方、薬を服用中の方などは医師に相談してから使用してください。
排便回数や便の状態から自身の体調を把握しよう
排便回数には個人差があり、1日3回〜1週間に3回程度であれば正常の範囲内です。1日に5回以上排便する方は下痢気味、1週間に1〜2回しか排便しない方は便秘気味と判断できます。
また、自身の健康状態は、排便回数だけでなく便の状態からも確認可能です。排便回数や便の状態に異常がある場合は、早めに医療機関を受診して医師の指示を仰ぎましょう。なお、便秘が続く際は、生活習慣の見直しでお通じが改善する可能性もあります。