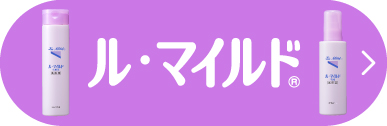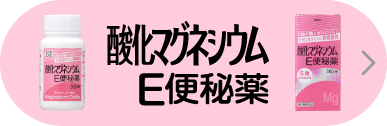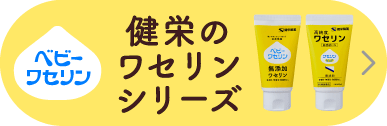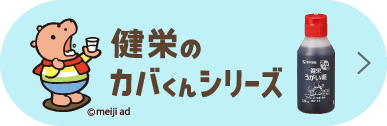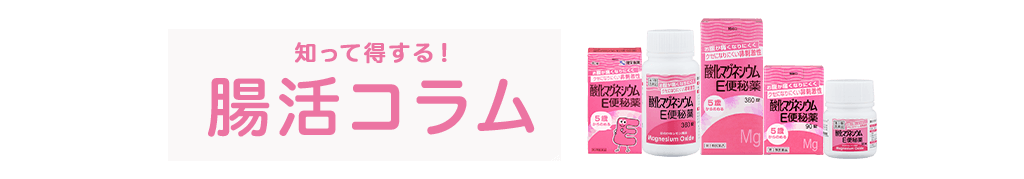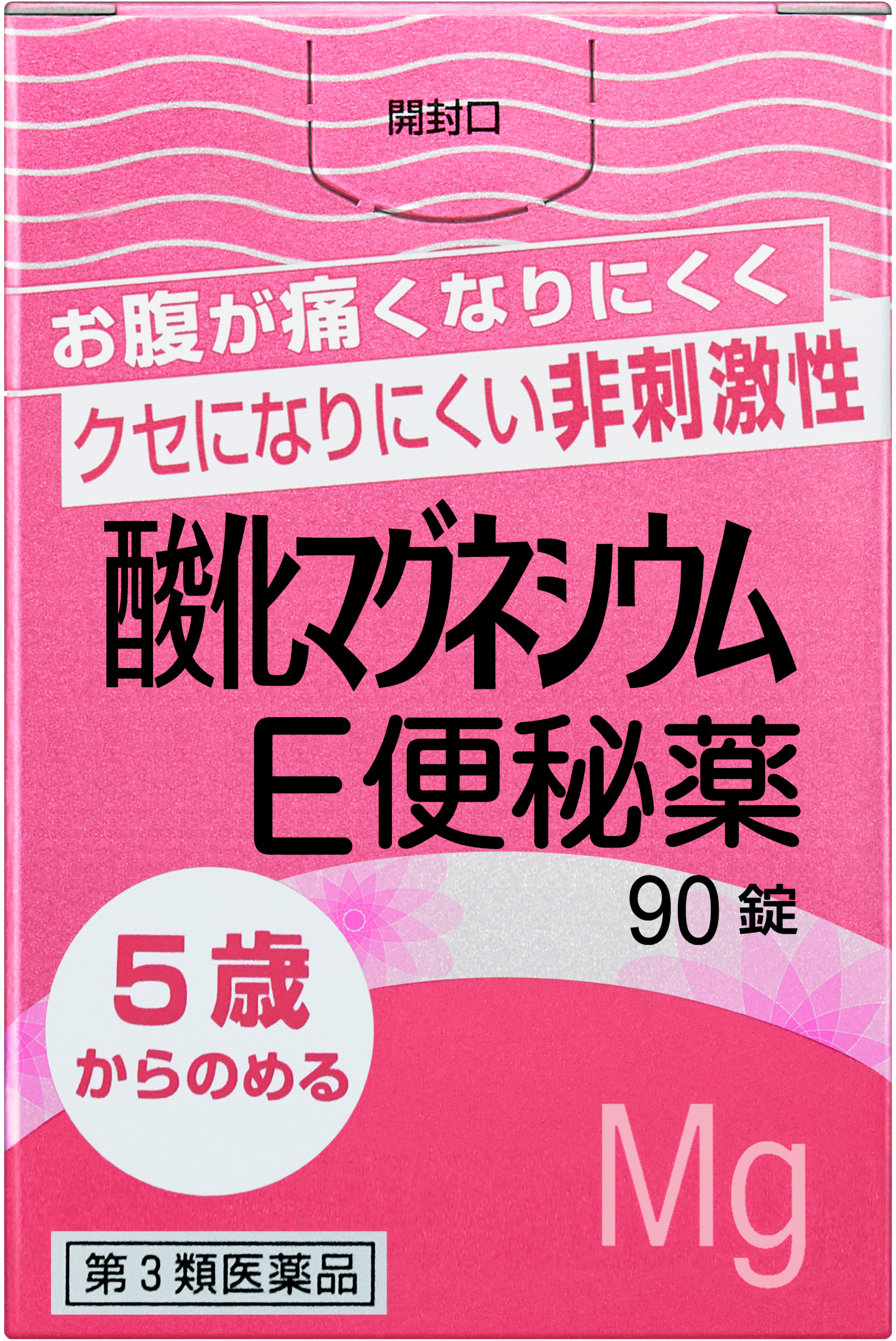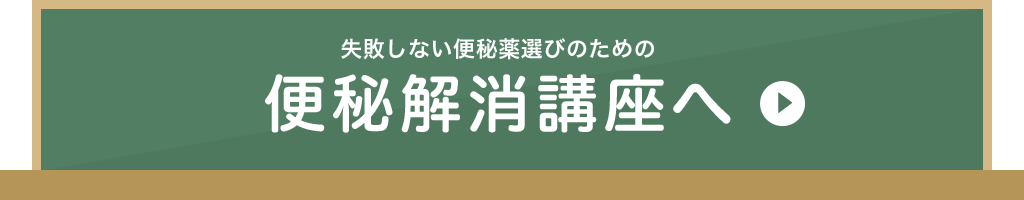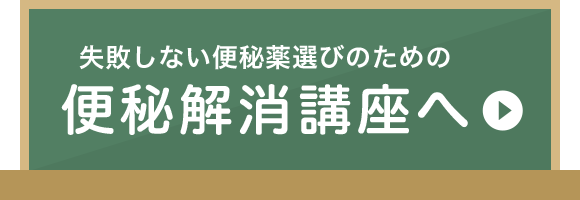VOL.175 【医師監修】便秘の種類や原因とは?生活習慣との関係性や改善方法を紹介

慢性的な便秘に悩んでおり、原因と対策が知りたいと思っている方は多いかもしれません。
便秘には種類があり、その種類によっては原因となる疾患の治療が必要です。また、胃腸の働きの低下によって便秘が疑われる場合は、食生活をはじめとした生活習慣の改善が必要となります。
今回は、便秘の種類や原因となり得る生活習慣、日常生活を改善するポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。
便秘の種類と原因
便秘は、「機能性便秘」と「器質性便秘」に大きく分かれます。それぞれの便秘の特徴や原因を以下に解説していきます。
胃腸の働きの低下により起きる機能性便秘
「機能性便秘」は、腸の働き(機能)が低下することによって起こる便秘です。
症状によって「排便回数減少型」または「排便困難型」に分類されています。また、機能性便秘は病態によってさらに以下の3種類に分類されています。
| 大腸通過遅延型 | 大腸が便を送達する能力が低下しているために排便回数が減少したり排便量が減ったりする便秘。何らかの疾患や薬剤の服用によってもこのタイプの便秘がおこる場合がある。 |
| 大腸通過正常型 | 大腸が便を送達する能力が正常にもかかわらず排便回数が減ったり排便量が減少したりする便秘。ダイエットなどにより食事摂取量が少ない方にみられやすい。 |
| 機能性便排出障害型 | 大腸の運動、知覚や反射、排便を司る筋肉の協調運動が障害されて生じる便秘。便意を我慢する傾向にある方や高齢者にみられやすい。 |
排便回数が減っているタイプの便秘なのか、排便時に硬くて排便が困難だったり残便感があったりする便秘なのか、これはご自身でもわかりやすい症状です。
一方で、大腸が正常であるか確認するには、専門的な施設での検査が必要になるため、便秘が続いている場合は専門施設を受診しましょう。
腸の形が変化することで起きる器質性便秘
器質性便秘は、大腸が狭くなったり太くなったりなど、大腸の形が異常に変化して起こる便秘です。
大腸は、便が通る道に例えられ、便が通る道が狭くなったり閉じてしまったり、異常に太くなったりすると、便がスムーズに送られにくくなります。
また、器質性便秘の場合は、便が通る道(大腸の形)に異常があるため、根本となる病気を治療する必要があります。
ただし、ご自身で器質性便秘なのかを判断するのは難しいため、便秘症状が長く続く場合は医療機関を受診しましょう。
便秘の原因になり得る生活習慣とは?
便秘の原因として生活習慣が関係することがあります。それぞれの原因について解説しますので、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
栄養の偏った食事ばかり摂っている
栄養の偏った食事を続けていると、便秘になりやすい傾向にあります。
例えば、砂糖をたっぷり使ったお菓子、動物性タンパク質が豊富な肉類、脂肪分の多い食べ物は、悪玉菌のエサになるので注意が必要です。また、アルコール飲料の摂りすぎも、腸内環境の悪化を引き起こします。
悪玉菌のエサになるようなものばかり食べていると、腸内環境が悪化し、便秘などの便通トラブルを引き起こしやすくなるため覚えておきましょう。
また、食物繊維が不足すると便秘になりやすくなるので、食物繊維もバランス良く摂取すると良いでしょう。
生活リズムが乱れている
生活リズムが乱れると便秘になりやすいと考えられています。
例えば、夜遅くまでスマートフォンなどを使っていると、交感神経系が活性化するため、就寝時には寝つきが悪くなったり、入眠できても十分な睡眠がとれなくなったりすることがあります。
また、生活リズムの乱れは、心身が交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズに行えなくなるおそれもあります。
大腸の働きは、交感神経と副交感神経のバランスで調節されています。規則正しい生活をすると神経反射がスムーズになりやすく、決まった時間に排便する習慣がつきやすくなります。
また、便意がなくても、毎日同じ時間に洋式トイレの便座に座るようにすると、排便習慣がつきやすくなります。
トイレに行くタイミングは、朝食後がおすすめです。朝食は胃腸への刺激となり、排便反射を促しやすくしてくれます。腸への刺激となるコーヒーや緑茶などカフェインを摂取するのも良いでしょう。
便意を我慢することが多い
便意を我慢することが多いと、便秘になりやすくなります。
腸のぜん動運動によって便が直腸に送達されると、その刺激が脳に届いて便意を感じます。便意を感じればトイレに行きたいという気持ちになりますが、我慢することが多いと、直腸に便が溜まっても便意を感じにくくなります。
トイレに行く動機がだんだんと薄れてしまうと、直腸に便が溜まってしまう状態になります。
授業中や仕事中は便意を感じてもすぐにトイレに行けず、一時的に我慢することもあるかもしれません。トイレに行けるようであれば、トイレに行って排便を試みることが、便秘を防ぐためには大切です。
運動量が不足している
運動量が少ないと、筋力が衰えていってしまいます。
とくに、腹筋まわりの筋力が低下すると腸のぜん動運動が弱くなり、便秘になりやすくなります。
運動量が低下しがちな高齢者や、デスクワークで運動不足の方は、腸のぜん動運動の低下によって便秘になることがあります。
また、腹筋が弱くなると排便時にいきむ力も低下してしまうので、スムーズな排便が難しくなることがあります。
機能性便秘は日常生活によって改善が期待できる

機能性便秘は大腸の働き(機能)が低下して起こる便秘です。大腸の働きを意識的に促すことで、機能性便秘になりにくい日常生活を送ることができます。
以下では機能性便秘の改善方法を解説するので、日常生活に取り入れられるものを実践してみてください。
腸内環境を意識して食事の内容を決める
腸内には多くの大腸菌が存在しています。まだまだ不明な点は多いですが、いわゆる善玉菌、悪玉菌、日和見菌と称され、以下の表に示すような役割があります。
とくに、善玉菌は腸の運動を活発にしてくれる働きがあるので、便秘を改善するためには善玉菌を増やすことがポイントです。
| 善玉菌 | 乳酸や酪酸を産生し、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。免疫を調整したり、腸粘膜のバリア機能を高めてくれたりします。 |
| 悪玉菌 | ガスや毒素を発生させ、腐敗物質を生成する働きがあります。発がん、肥満、アレルギー疾患の原因と考えられ、老化を早めることもあります。 |
| 日和見菌 | 大腸の状況によって善玉菌か悪玉菌のどちらか優勢な方に味方します。 |
腸内環境を良い状態に保つためには、善玉菌にとって良い環境に、悪玉菌にとって苦手な環境にしてあげることがポイントです。
例えば、善玉菌のエサになるもの(以下の表)を意識的に摂取すると良いでしょう。
| 水溶性食物繊維 | ひじきなどの海藻類、キノコ類、イモ類、大麦、豆類など |
| 乳酸菌や納豆菌 | ヨーグルト、チーズ、納豆など |
| ビフィズス菌 | ヨーグルト、チーズ、漬物、キムチ、みそなど |
| オリゴ糖 | きなこ、ごぼう、玉ねぎ、にんにく、バナナなど |
無理のない範囲で運動する
適度な運動をすることで自律神経系が刺激され、ぜん動運動が促進されることが期待できるため、便秘の解消につながります。
また、運動は日頃のストレスを解消することにも一役買ってくれるでしょう。
ただし、いきなり激しい運動をする必要はありません。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を30分から1時間程度、日常的に行っていくことが大切です。
ほかにも、腹筋運動など、屋内でもできる運動もおすすめです。腹筋は、便の排出をスムーズに行うために、日頃から鍛えておくと良いでしょう。
酸化マグネシウム便秘薬を試してみる
酸化マグネシウム便秘薬によって機能性便秘を解消できることがあります。
ただし、便秘薬だけに頼らず、生活習慣を改善しながら酸化マグネシウム便秘薬を試していくことが重要です。
酸化マグネシウム便秘薬は、腸管内に水分を引き寄せる作用があり、その水分によって便をやわらかくし、スムーズな排便に導きます。また、クセになりにくく、お腹が痛くなりにくいのも特徴です。
ただし、腎機能が低下しているなどの持病がある方や、ほかの薬を服用している場合には、医師や薬剤師に相談してから服用しましょう。
なお、健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」はオンラインショップでも購入できるので、ドラッグストアに行くのが難しい方やお店で便秘薬を購入するのに抵抗がある方は、ぜひ検討してみてください。
https://kenei-online.shop/collections/ebenpi
便秘の種類や原因を知って予防・改善を目指そう
便秘には、機能性便秘と器質性便秘があり、それぞれ便秘になる原因が異なります。
機能性便秘は、食生活や運動習慣を見直すことで改善が期待できますが、器質性便秘は根本となる病気を治療する必要があります。
偏った食事や生活リズムの乱れ、便意の我慢や運動不足は、機能性便秘につながるので注意が必要です。
腸内環境を意識した食事や運動習慣で、機能性便秘の解消が期待できます。なかなか便秘が改善しない場合には、酸化マグネシウム便秘薬を試してみるのも良いでしょう。
生活習慣の見直しと便秘薬を上手に活用して、便秘の改善を目指しましょう。
- 高山医師よりコメント
- 便秘はさまざまな要因で発症します。なかには、重大な疾患も隠れているため、一度はご相談になると良いでしょう。腸内細菌の研究も進んでおり癌や肥満、糖尿病との関連も一部わかってきている一方、不明な点も多いので怪しい情報に騙されないようご注意ください。
- 監修者
-

医師:高山 哲朗
かなまち慈優クリニック 理事長
平成14年慶應義塾大学卒業、慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長。医学博士。日本内科学会総合内科専門医。日本消化器病学会専門医。日本消化器内視鏡学会専門医。日本医師会認定産業医。東海大学医学部客員准教授。予測医学研究所所長。