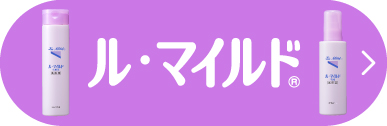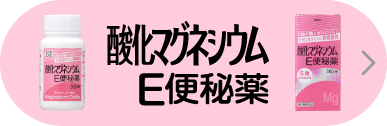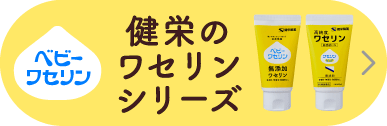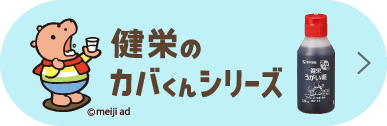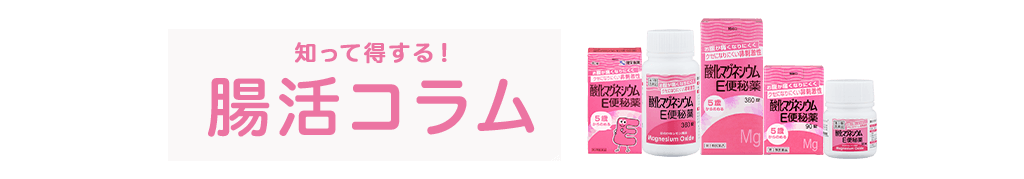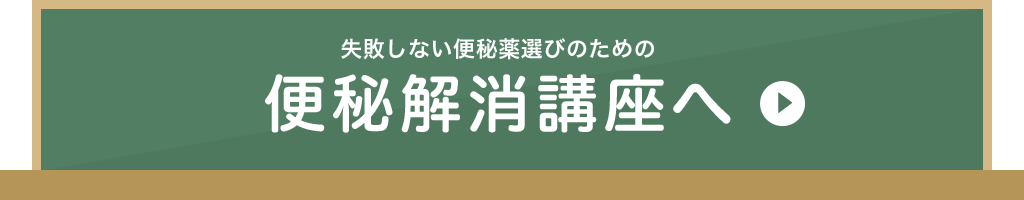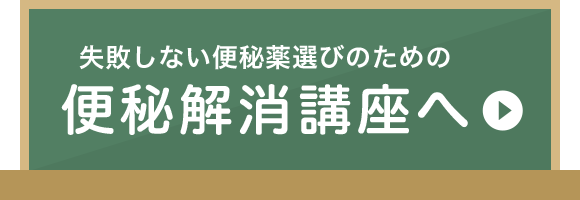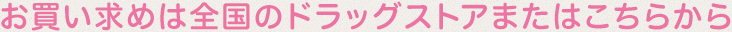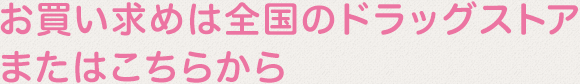VOL.144 【医師監修】浣腸後に気持ち悪いと感じる原因は副作用?適切な対処法を解説

直腸付近に溜まった便をすっきり排泄したいときに使う浣腸薬。浣腸すると腸の活動性があがるので、お腹が痛くなったり、お腹に溜まったガスが移動してゴロゴロとお腹が鳴ったりしますが、こうしたお腹まわりの現象だけでなく、めまいや吐き気を感じてしまう場合があります。
実際に自身や家族が浣腸を使用した後、急に気持ちが悪くなり、焦った経験がある方もいるのではないでしょうか。
今回は、浣腸後に気持ち悪さや吐き気が起きる原因とその際の対処法を紹介します。また、浣腸使用時の注意点や浣腸以外に自身で試せる便秘解消法も紹介するので、あわせて参考にしてください。
浣腸の使用後に気持ち悪くなる原因は?
浣腸を使用した後に、吐き気や体調不良が起きた場合、それは副作用の可能性があります。これは浣腸行為によって迷走神経反射が起こるためです。
迷走神経反射とは、腸に分布する迷走神経を介して血管運動を調節する脳幹の中枢神経が刺激されることで、心拍数が低下したり、血圧が低下したりする生理反応です。この反射によって、気持ち悪さ、めまい、ふらつきなどの症状が現れます。
浣腸行為によって迷走神経反射が起こる要因には、以下があります。
- 1.浣腸器のチューブを肛門に挿入する。
- 2.浣腸液を注入するスピードが速すぎる。
- 3.浣腸後に便意が強まるまで我慢を強いられる。
急に心拍数や血圧が低下すると、一時的に血液が脳血管に十分に送られなくなるので、ひどい場合には失神に至ることもあります。
そのため、浣腸後に気持ちが悪い、めまい、ふらつき、冷汗、血の気が引いたような顔色をしているといったような症状が現れた場合には、その場で横になり、脳への血流量を確保するようにしましょう。横になれない状況では、頭の位置を少しでも低くなるようにしゃがんで休みましょう。そこで頑張って立っていると、失神が起こったり、突然倒れて地面に頭を打ちつけたりしてしまう危険性があります。
どれくらいの割合で気持ち悪さなどが発生するのかは明確ではありませんが、浣腸後にそうした症状が出ていないか注意し、気になる症状が出ればすぐに排泄し、からだを横にして落ち着くまで安静にするなどの行動をとるようにしてください。
副作用のリスクを最小限に抑える!浣腸使用時の注意点
副作用のリスクを最小限に抑えて浣腸を使うための注意点を3つ紹介します。
使用に不安がある方は、事前に医師や薬剤師に相談する
持病のある方や妊娠中の方、ほかの薬を服用中の方、浣腸の使用に不安がある方などは、医師や薬剤師にあらかじめ相談して、使用するかどうかを検討しましょう。
肛門周辺部に痔があったり、出血傾向があったりする方は、浣腸の使用を避けなければなりません。
持病のない方でも、体調が悪いときには使用を控えるようにしましょう。
浣腸液は適量を適切なスピードで注入する
浣腸液は医師の助言や商品の説明書を参考に適量を注入するようにします。余った薬液は再使用せずに廃棄し、万が一多く注入した場合は医師に相談してください。
浣腸液を注入するスピードが速いと迷走神経反射が起こる場合があるので、注入するスピードはゆっくりを意識しましょう。例えば30g容量の製品であれば10秒程度の時間をかけて注入しましょう。
注入後に便意が強まるまで排泄を我慢するのですが、我慢のしすぎは禁物です。注入後1~3分程度でも十分に便意が強くなりますので、無理をせずにその時点で排泄するようにしましょう。
浣腸は人肌程度に温めてから使用する
浣腸を使用する際は、あらかじめ湯煎で人肌程度に温めることを心がけましょう。
なぜなら、浣腸液を冷たい状態で注入すると、使用後の血圧変動が起きやすくなる可能性があるからです。また、浣腸液を熱くしすぎると、注入時に直腸の粘膜を損傷する(炎症を起こす)可能性があるので、浣腸液の温度には注意しましょう。
浣腸以外に試せる便秘の解消方法

浣腸の副作用に不安がある場合は、無理やり浣腸をする必要はありません。
浣腸以外に自身で試せる便秘の解消法を以下で解説するので、できそうなものから試してみてください。また、これらは便秘を予防することにもなるので、日常生活に取り入れてみてください。
意識的に水分を摂取する
水分の摂取量が少ないと便が硬くなり、便秘の原因になることがあります。便秘が気になる方は、1日2リットルの水分を意識的に摂取するのが良いでしょう。
水分の種類として、利尿作用のある緑茶、コーヒー、紅茶などよりも、水や白湯、麦茶などを飲むのがおすすめです。また、起床後すぐに水分を摂ると、腸が活発に動きやすくなる効果も期待できます。
適度な運動習慣をつける
適度な運動により、腸の蠕動運動を促す効果が期待できます。まずはウォーキング、ジョギング、水泳などの全身運動や腹筋運動を試してみましょう。腹部の筋肉を鍛えれば、腸の動きや排便をサポートしてくれます。
また、運動はストレス解消にもなります。規則的な生活リズムを整えることで、便秘改善につながる可能性もあります。
食物繊維の多い食事を摂る
食物繊維には、便を柔らかくし、便のかさを増やして排便を促す効果が期待できます。食事量が減って排便回数が減少している方におすすめです。便のかさが増えることで、腸の動きを促し、お通じの改善が期待できますが、慢性的に硬い便で悩んでいる方は不溶性食物繊維を多く含む食材をたくさん摂取すると、便秘を悪化させる場合があります。
食物繊維の多い食材は、穀物や芋類、果物、生野菜、きのこ類、藻類などです。1日に20g前後を目安として食物繊維を摂取しましょう。
酸化マグネシウム便秘薬を服用する
酸化マグネシウム便秘薬は、便を柔らかくして排出しやすくする効果があります。浣腸より効果の現れ方がゆるやかで、多めの水と一緒にお薬を服用すると良いでしょう。
酸化マグネシウム便秘薬はクセになりにくく、お腹が痛くなりにくいのが特徴です。ただし、胃薬や抗生剤などの薬を服用している方は、酸化マグネシウム便秘薬を服用しても問題がないかを医師や薬剤師に事前に相談し、用法用量を守って正しく服用しましょう。
浣腸の使用後に気持ち悪いと感じたら、早めに医療機関を受診しよう
浣腸の使用後は、まれに副作用が出る可能性があります。すぐに症状が治まらない場合には、早めに医療機関を受診しましょう。
副作用のリスクを極力抑えるには、体調不良時に使用しない、薬液を人肌程度に温める、適量をゆっくり注入するなどの複数のポイントがあります。
浣腸に対して不安が大きい場合は、無理に浣腸を使わず、酸化マグネシウム便秘薬や生活習慣の改善を検討してみてください。
- 白畑医師よりコメント
- 便秘に悩む方は日常生活改善・適切な食事・運動を心がけ場合により投薬や医療機関を受診しましょう。また、排便困難型の直腸性便秘の解消の1つとして浣腸は有効であり、身体的な依存は無く適切な使い方・気持ち悪いと感じる原因や対処法を熟知し、便秘予防に取り組んでいきましょう。
- 監修者
-

医師:白畑敦
昭和大学医学部を卒業後、昭和大学藤が丘病院、市中病院で消化器外科医として勤務。大腸肛門病疾患でも研鑽を積み、2017年しらはた胃腸肛門クリニック横浜を開設。大腸疾患(内視鏡治療・便秘治療・炎症性腸疾患など)・肛門疾患(痔核手術・便失禁治療など)を専門分野として診療。